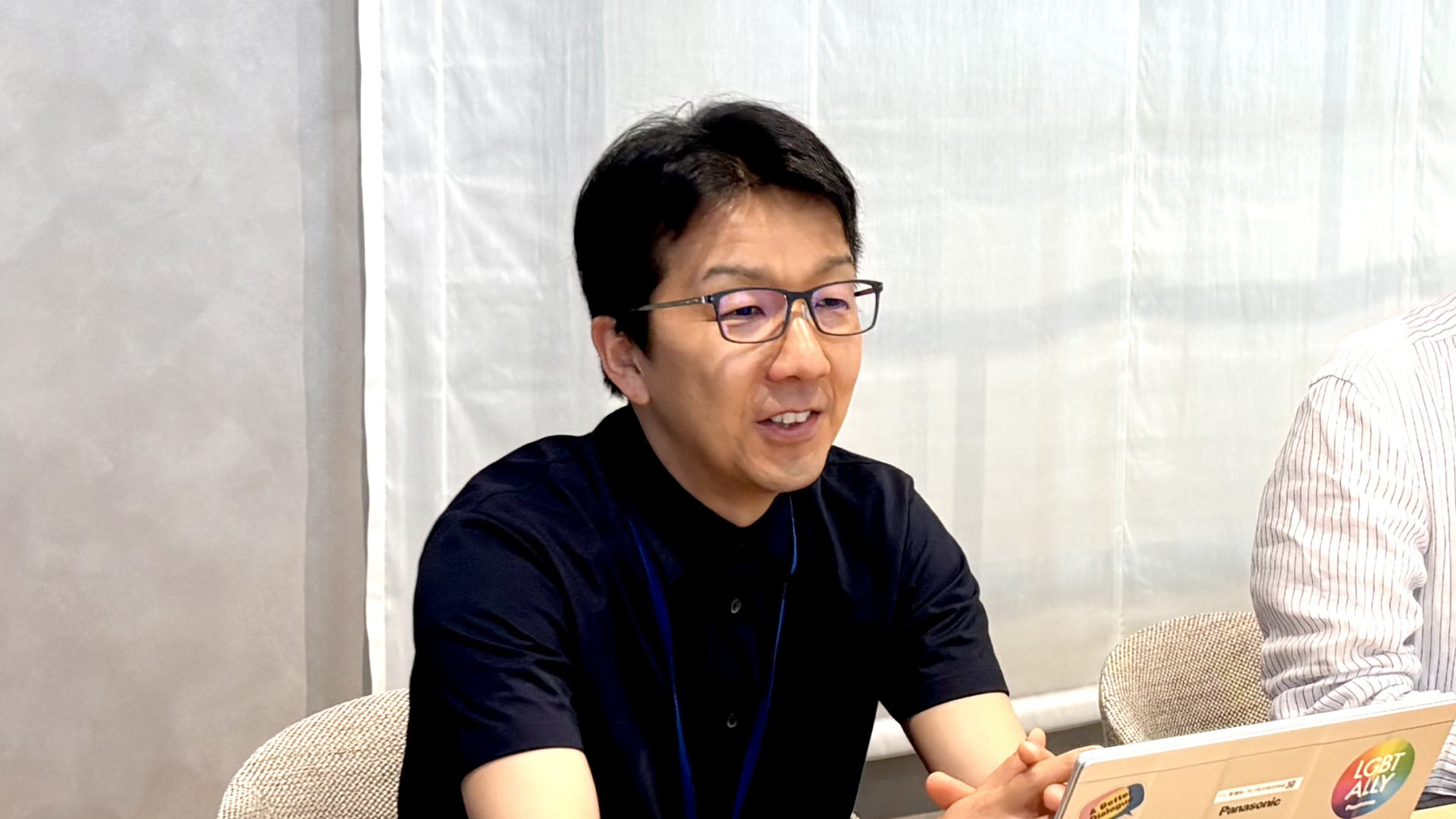Panasonic新拠点で実現!自由と安心が両立する“つながる職場”
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
- 効果
-
- ハイブリッドワーク下でも、出社状況をすぐに把握できる
- 「今どこにいる?」がすぐわかり、対面コミュニケーションが増加
- 居場所共有で「つながる安心」を確保。フリーアドレスの定着を促進
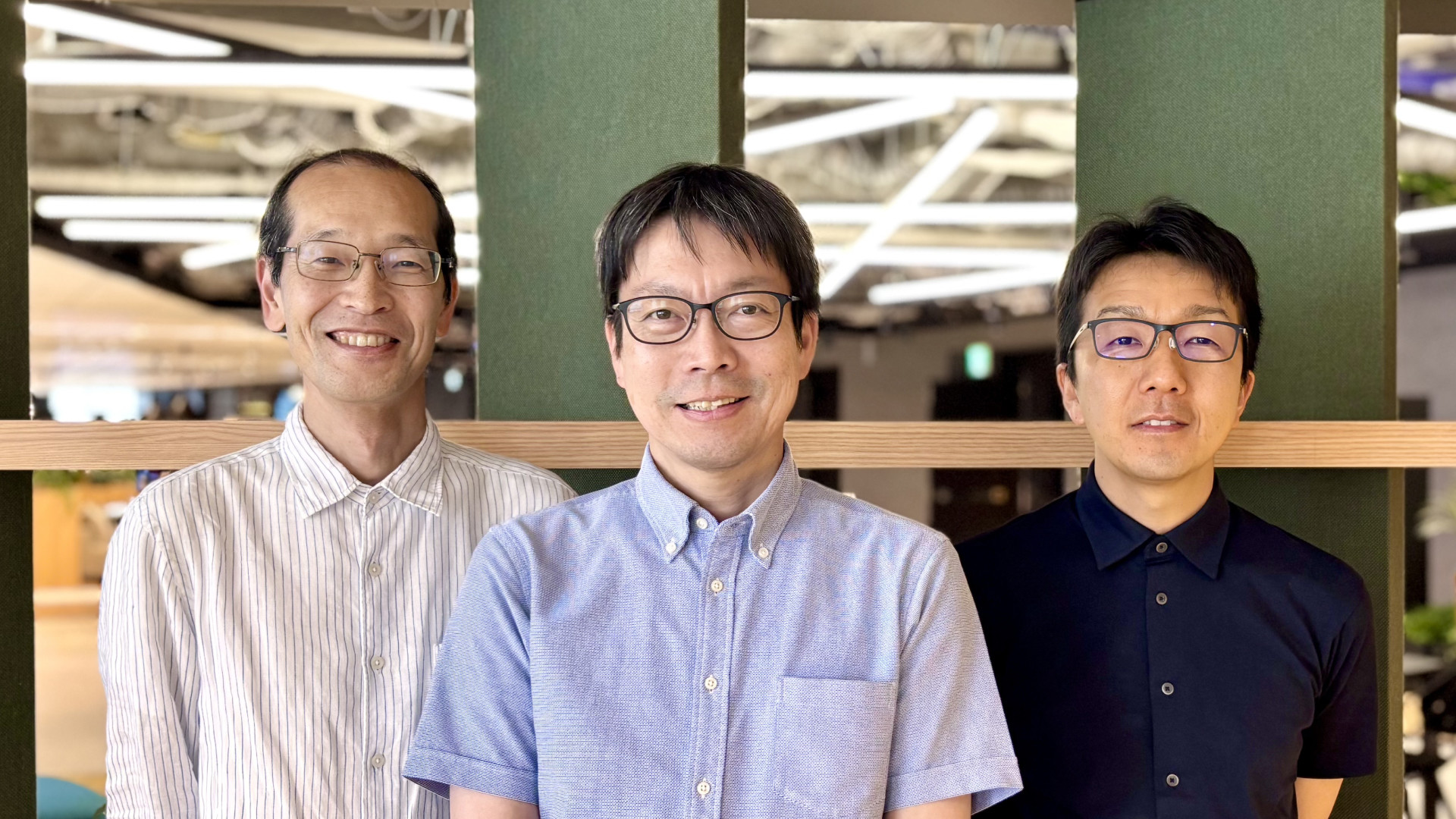
「デジタルで、幸せをつくろう。」を企業理念に掲げる「パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社」は、パナソニックグループのIT事業会社として、グループ内外に最適なトータルソリューションを提供しています。
2025年2月、大規模なオフィス移転を機に、すでにグループ全体で利用していたコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」(以下、PA PEOPLE)を基盤として、オフィス内での居場所共有サービス「PHONE
APPLI
PLACE」(以下、PA PLACE)を利用開始していただきました。
リアルとリモートの混在する新しい働き方のなかで、「自由」と「つながる安心」の両立をどう実現したのか。総務部門の大久保正顕氏および高城孝典氏、システム部門の真本昌幸氏にうかがいました。
※ 本記事でご紹介している新オフィスは、2025年度第38回日経ニューオフィス賞「ニューオフィス推進賞」を受賞されました。
オフィス移転とともに始まった、働き方変革への挑戦
──まず、新オフィスへの移転の背景を教えていただけますか。
大久保氏 当社は、もともと大阪市内に8拠点を構えていたのですが、それらを統合して2025年2月に「Panasonic
XC OSAKA」へ移転しました。これを機に、アプリ部門、インフラ部門、直轄部門、営業部門の社員、約920人が同じ拠点で働けるようになりました。パナソニックグループ全体のDX戦略「Panasonic
Transformation(PX)」を進めるなかで、それを体現する場として位置づけています。
──PXでは、どんなことを重視されているのでしょうか?
大久保氏 PXは、パナソニックグループ全体で、「IT」「オペレーティング・モデル」「カルチャー」の3つの視点からの組織全体の変革をし、持続可能な成長を実現するというものです。一般的なDXでは、ITやオペレーションの面が強調されることが多いかと思いますが、私たちはカルチャー面、つまり人の意識や行動のあり方についてもあわせて変革していこうというのを大事にしています。
──この新オフィスには、PXの実践はどのように反映されていらっしゃいますか。
大久保氏 まず、移転プロジェクトのはじめには、社員が主役となって「どう働きたいか」「どうありたいか」を話し合うワークショップを複数回実施し、そこからオフィスのあり方を練っていったんです。参加メンバーは約30名で、今日インタビューを受けている真本さんも参加してくれました。
──そうなのですね。真本さん、ワークショップに参加してみていかがでしたか?
真本氏 そうですね、ある意味、無邪気な意見をどんどん出し合いましたよ。それまでの働き方の、よい点と課題点をどんどん洗い出して、理想の働き方をシナリオで描いていきました。例えば、朝ここでコーヒー飲みながら雑談しつつ勤務開始して~、とか、集中ブースで大事な資料を作り終えたら、テラス席で仕事して気分転換して~、とかね。
──社員の方々が自分ごととして空間の使い方を考えていったのですね。
大久保氏 そうですね。この話し合いのなかで浮かび上がった「ユニーク」と「多様性」というキーワードを、このオフィスのコンセプトとして位置づけました。それが、バリエーション豊かなエリア設計や、気分や業務内容に応じて働く場所を選べるABW(Activity
Based Working)の考えに基づくフリーアドレス運用にも反映されました。
──エリアのバリエーションは、どのように設けているのですか?
大久保氏 はい、2階から8階の各フロアのレイアウトは同じなのですが、カーペットや壁の色合いや材質、什器に変化をつけています。各フロア内にも、様々なコンセプトの会議室があるほか、昇降デスクやファミレス席、電話ボックスなど多様なエリアを設けています。9階は来客も利用できる共用スペースです。これらの多様なワークスペースを、その時の気分や状況に応じて自ら主体的に選ぶことで、より気持ちよく生産的に働き続けられると考えています。
──コミュニケーションの面でも、理想とするあり方は話し合われましたか。
大久保氏 そうですね、以前は8拠点に分かれていたので、リモートの打ち合わせはできると言いつつも、やはり対面でのコミュニケーションの情報量には及ばないところがありました。そのため、同じ場所に集い、リアルな接触を増やすことで、コミュニケーションの活性化や新しいアイディア創出を促進したいという願いは、多くの社員が共通して持っていました。
-

「Panasonic XC OSAKA」8階 執務フロア -

同9階 来客・共用エリア「POLYGON PARK」
PA PLACE導入の背景にあったニーズ
──オフィス内の居場所情報を把握したいというニーズは、オフィス開設前から感じていらっしゃったのですか。
大久保氏 はい、フリーアドレスの運用を開始するにあたっては、2階から9階にわたる広いオフィスで「誰がどこにいるか」の把握が困難になることは明らかだったので、居場所共有システムが必要だと考えていました。
高城氏 また、そもそも出社率は50%程度を想定していたので、その日の出社状況を簡単に把握したいというニーズも予想されましたね。
大久保氏 そうそう、その通りです。あと、根本的な話としては、フリーアドレスを導入したとしても、ただルール上「自由に席を選んでよい」とするだけでは、うまく機能するのかわかりませんでした。というのも、長年、固定席で仕事されてきた社員も多いのと、社風として、他の社員が訪ねてきたときに、「いつもの席」にいないと不便をかけるのではないかと気遣うあまり、自由に動けない人もいるのではないかと……。
──たしかに、いざ自由に動いてと言われたときに、習慣や周囲への遠慮がハードルになることはありますね。
大久保氏 そういう意味で、PA
PLACEで居場所を共有して、オフィスにいるならすぐに会いに行けるし、いないならすぐに他の手段で連絡できる、という状況を作り出すことができれば、不安や遠慮を感じずに自由な場所を選ぶ後押しができるのではないかと考えました。
──なるほど、自由で柔軟な働き方を推進するために、「つながる安心」を担保したのですね。
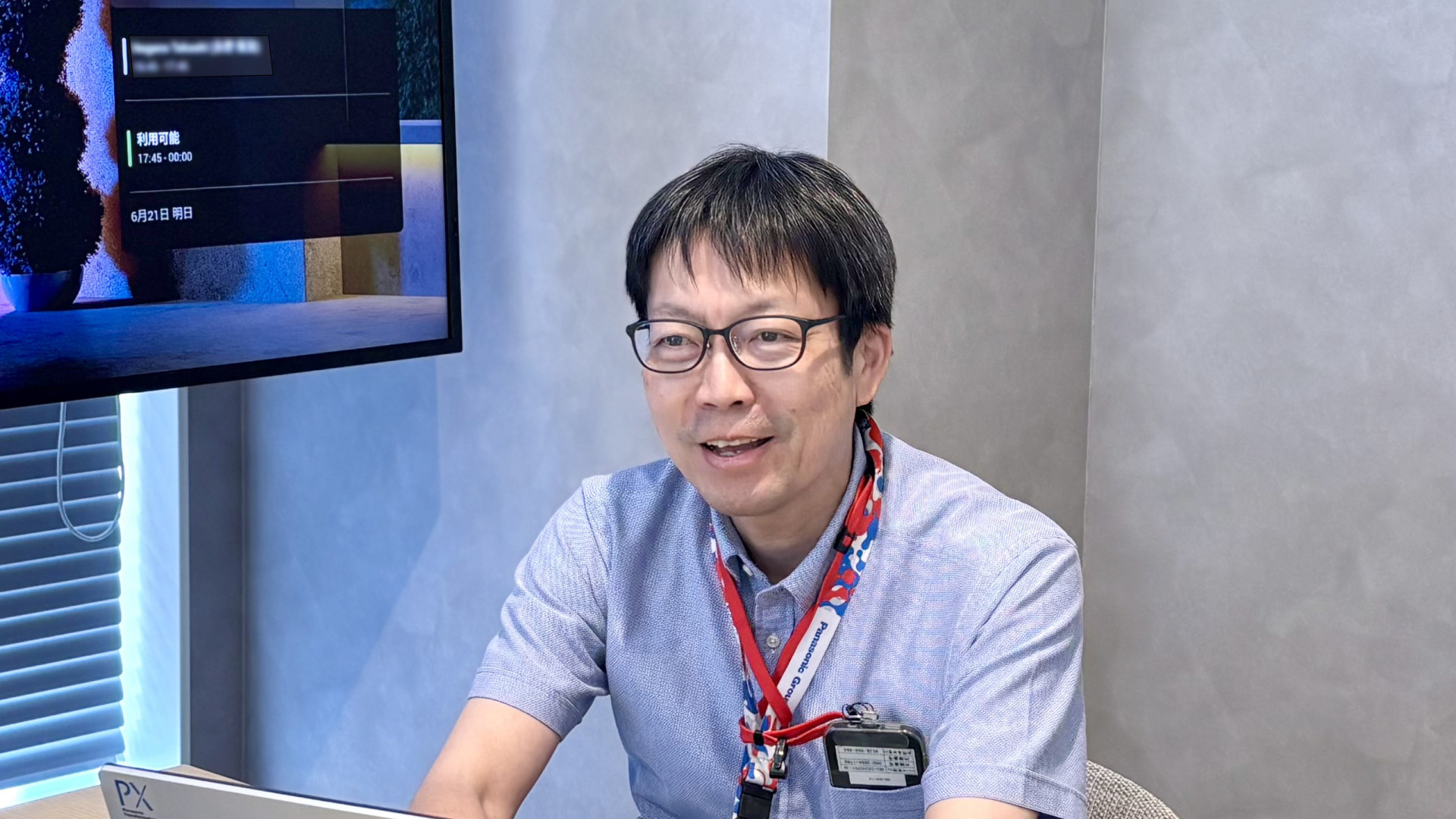
導入時のハードルと乗り越えた工夫
──PA PLACEの導入はどのように進められたのでしょうか。
大久保氏 サービスの選定は、初めからPA PLACEで決めていました。グループ全体で利用しているPA
PEOPLE上で使用できることと、当社が採用しているWi-Fiシステムとの連携で位置情報を取得できるという利点があったからです。さらに、位置情報に加えてPA
PEOPLEの他機能(連絡先、所属、担当業務等のプロフィール情報)を併用することでコミュニケーションの活性化の効果も期待できるというメリットもありました。
真本氏 私は2022年のグループ全体でのPA PEOPLEの導入や、他拠点でのPA PLACEの導入も手掛けたことがあり、PA PEOPLEとPA
PLACEを使うメリットがすでにわかっていたので、社内にも説明がしやすかったですね。
──ありがとうございます。では、今回のPA PLACE導入はスムーズに進みましたか?
真本氏 いや、それでも多少、ハードルがありました。当初は、プライバシーへの配慮から、「希望者制」で導入すべきだという意見もあって。ただ、利用効果を発揮するためには利用者数を大きく確保しないと意味がなくなってしまうので、どうにか調整をつける必要がありました。それで、情報セキュリティ部門と話し合いをして。高城さんが話してくれたんですけどね。
高城氏 はい、プライバシーへの配慮と利便性の折り合いをつけるために、「原則一括登録して、登録してほしくない人がいれば申し出ていただく」という方式でいきますとお話しをして、納得いただけました。
つながる安心を支えるPA PEOPLE/PA PLACE
出社状況と居場所が一目でわかり、対面コミュニケーションが増加
──実際にPA PLACEを利用してみて、効果はどのように感じていらっしゃいますか。
真本氏 そうですね、「今日は誰が出社しているのか」「どこにいるのか」が一目で分かるようになりました。朝、オフィスに来たらまずPLACEを見て、チームメンバーがどこにいるのかを把握するところから始めますね。オフィスにいることがわかったら、打ち合わせやちょっとした相談も、チャットするより直接会いに行くことが増えました。
──顔を合わせて話してよかったな、と思うことは多いですか?
高城氏 よくありますね。特に調整ごとや繊細な内容は、顔を合わせて話す方が断然スムーズです。あとは、チャットでやりとりをしていて「なんかボタンの掛け違いが起こっていそうだな」と感じたときには、すぐに会いに行って話すようにしています。
それと、単純に、これまで拠点が離れていた人と顔を合わせて会話する機会ができたことで、仕事のことで直接「ありがとう」と言ってもらえたりすると、うれしいですね。
──それはとてもうれしい瞬間ですね。
真本氏 チャットして終わりというやり方もできなくはないんですけど、実際会うことで新しい感情やアイディアが生まれるっていうのは、実際にあると思っています。

「あの人、どこにいる?」「この人、誰だっけ?」をなくす安心感
──フリーアドレス運用での不安を解消することには、役立ちましたか?
真本氏 やっぱり、PA
PLACEを見たらどこにいるかすぐわかると思うと、遠慮なく移動できますね。これがなかったら、チームメンバーが相談したいときに居場所がわからなかったら困るだろうと思って、いつも同じ場所で働いていたかもしれません。
高城氏 私も問い合わせを受けることが多い職種ですから、同じように感じています。もう一つ、前に座っている人が誰だかわからないときに、PA
PLACEでアイコンを確認して、そこからPA
PEOPLEのプロフィールを見れば、名前も部署もわかるので助かっています。
──大規模なオフィスだと、顔と名前が一致しない人も多そうですね。社員のみなさんも、フリーアドレス運用には慣れてこられましたか?
大久保氏 現在は、フリーアドレス運用ではあるんですが、部門ごとに「ホーム」的なフロアも割り振っています。ただしそこに毎日いる必要はなく、どのフロアにでも自由に移動して仕事してよいというルールです。というのも、別拠点から複数の部署が集合した部門もあるため、まずは部門内での対面コミュニケーションも促していく意図がありまして。
そういう背景もあり、今はまだ同じフロアにとどまって仕事をしている人も多い状況です。ただ、部門ごとでも人数が多いので、「この人、誰だっけ?」ということもよく起こるんです。そのため、PA PLACEで調べてPA
PEOPLEのプロフィールを確認するというのは多くの社員にとって安心感をもたらすツールになっています。
離れた拠点やグループ内の別事業会社とも「同じチーム」で働ける
──大阪本社以外でもPA PLACEを活用していらっしゃいますか?
大久保氏 はい。東京の浜離宮オフィス(約170名が利用)でも同様に活用しています。異なる拠点にいる社員同士でも、居場所が分かっていると、物理的距離を意識せずに連携できます。出張などで拠点間を相互に移動する場合もありますので、その際の居場所の共有にも役立っています。その意味で、離れた拠点間でも「つながる安心」を保ち、「場所にとらわれない自由な働き方」を実現する土台になっています。
──ありがとうございます。「離れた拠点」での連携という点に関連して、グループ全体(約24万ID)でご利用いただいているPA
PEOPLEについては、グループ内連携によい影響を与えていますでしょうか?
大久保氏 はい、本当に便利に感じています。他事業会社の社員に関しても、自社の社員と同じように所属や連絡先、担当業務等を見られるので、同じ会社の一員のようにすぐに相談ができます。初めてやりとりする相手でも、事前にプロフィールやスケジュール情報を把握できるので、スムーズなコミュニケーションができます。
高城氏 私も全く同じで、会社の枠を超えて、役割や人となりを把握したうえで、すぐに連絡がとれる環境はすごく仕事がしやすいですね。
今後の展望:データ活用とカルチャー変革を見据えて
データを“経営資源”に、次なる活用のステップへ
──今後のPHONE APPLI活用について、どんな展望をお持ちですか?
大久保氏 まずは、利用データの自社での活用です。例えば、PA
PLACEのログから会議室の使用状況を分析して、いわゆる“会議室難民”が生まれるのを防ぎたいと考えています。また、社員の滞在エリアごとの傾向を元に、空調や照明を最適化することも検討しています。
真本氏 さらに言えば、社員の行動パターンと成果の関係を分析して、よりいきいきと、よい成果を上げる働き方を探ることもできると考えています。そのような経営に対する価値を示すことが、システム部門としての使命であるとも思っています。
──ありがとうございます。オフィス改善から経営資源まで、可能性が広がりますね。
人と人がつながって変わる、職場の未来へ
──現在、一部の部門でトライアルしていただいているPA THANKS(PA
PEOPLE上で使えるサンクスカード機能)の活用についてはいかがでしょう?
真本氏 自己開示や感謝のやりとりが自然に生まれる職場は、心理的安全性も高まると感じています。ただ、使い方や価値が社員に十分に伝わっていないのも事実です。運用方法や活用・浸透のヒントについては、ぜひPHONE
APPLIのみなさんにも知見を借りたいですね。
──ありがとうございます。ぜひ引き続きお力添えさせていただければ幸いです。
真本氏 知見の提供や支援については、PA PEOPLEの活用全体について期待しています。PA
PEOPLEは単なる便利ツールではなく、「人が交わることで生まれる化学反応」を支えるインフラなんですよね。でもその価値を真に社内外に伝えることができていないと感じています。
「人と人をつなぎ、コミュニケーションを活性化させる」「自己開示を通じて信頼関係が深まる風土を作る」というツールとしての価値をさらに訴求して、PA PLACE等の、まだグループ内で標準化されていない機能の展開など、PA
PEOPLEのさらなる「使い倒し」を他事業会社でも推進していきたいと考えています。
大久保氏 たしかに、今回の新オフィスに導入したPA
PLACEも、単なる位置情報の共有サービスというよりも、社員一人ひとりが「どう働きたいか」に向き合い、「環境を選べる自由」と、必要なときに誰かと「つながれる安心」の両立を支えるという役割を担っていましたね。
真本氏 単なる便利ツールではなくカルチャー変革を実現する土台として訴求するための具体的な知見の提供など、PHONE
APPLIにはさらなる支援を期待しています。
──PHONE
APPLIの価値に対して、こんなにも深い理解をいただき、心から感謝いたします。いただいたご期待を胸に、活動を続けてまいります!