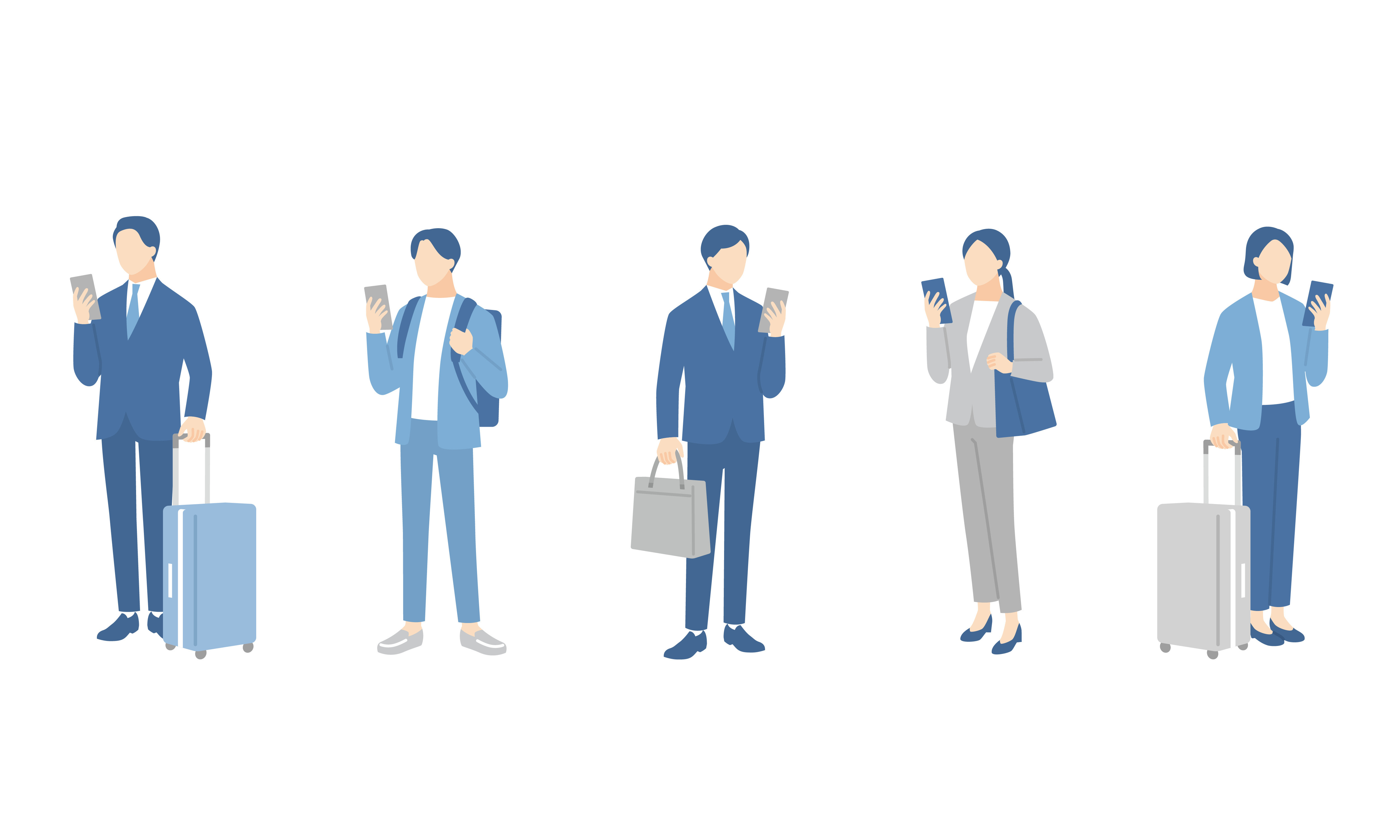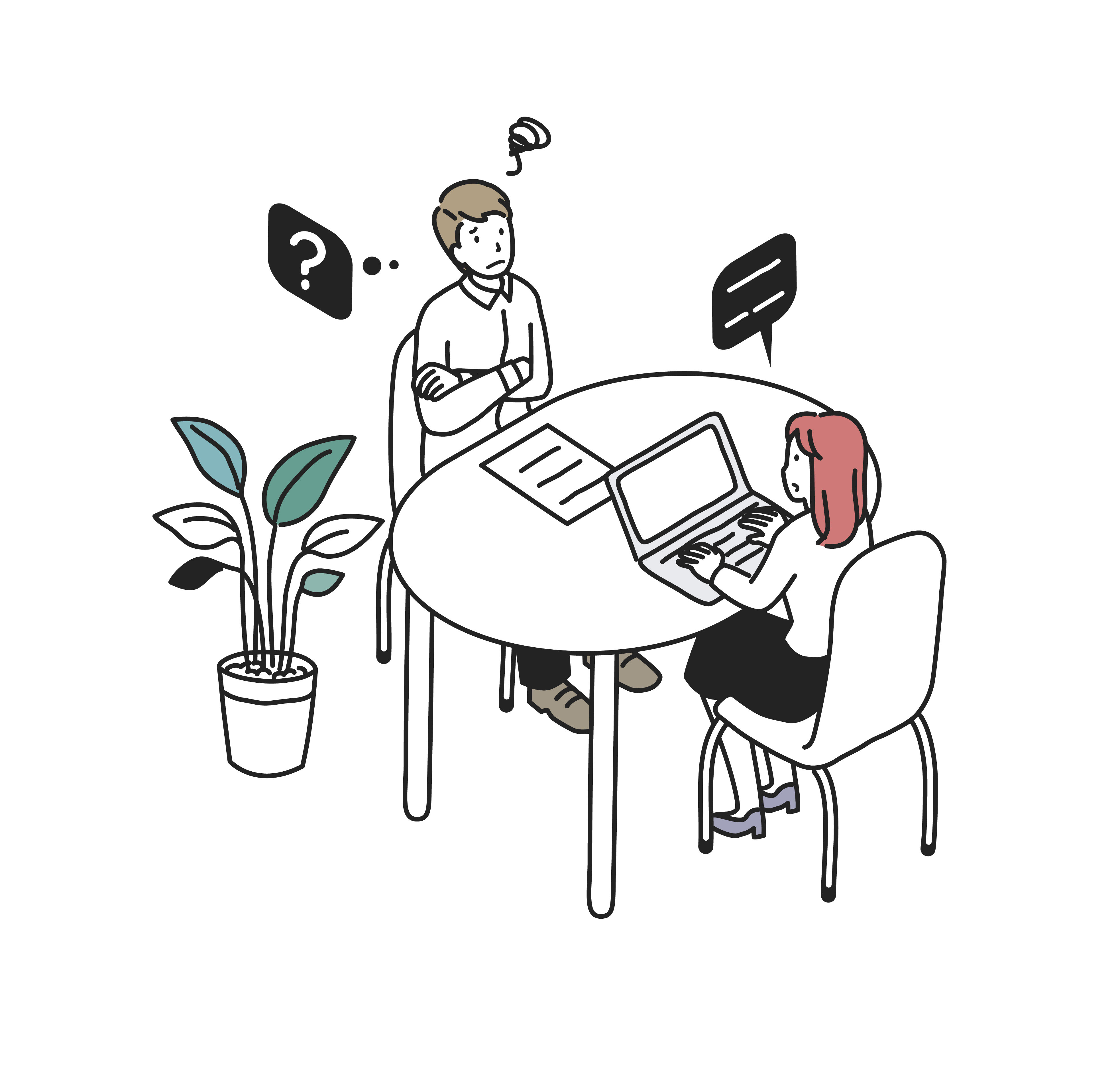グループアドレスとは?フリーアドレスとの違いや導入メリットを事例と共に解説

オフィスのあり方を見直す中で、「フリーアドレス」の導入を検討したものの、チームの一体感が薄れたり、マネジメントが難しくなったりするのではないかと、導入に踏み切れない企業は少なくありません。
そのような課題を解決する選択肢として、今「グループアドレス」が注目されています。
本記事では、グループアドレスの基本的な知識から、フリーアドレスとの違い、具体的なメリット・デメリット、そして導入を成功させるためのステップまでを分かりやすく解説します。
グループアドレスとは?フリーアドレスとの明確な違い
近年、働き方の多様化に伴い、オフィスの形態も変化しています。
その中で注目される「グループアドレス」について、まずは基本的な定義と、よく比較される「フリーアドレス」との違いを明確にしましょう。
グループアドレスの基本的な定義
グループアドレスとは、部署やチームといったグループごとに大まかな働くエリアを決め、その指定されたエリア内であれば、社員が自由に席を選んで働けるオフィススタイルです。
従来の固定席とは異なり、毎日同じ席に座る必要はありませんが、完全に自由なわけではなく、所属するチームのエリア内で活動します。
これにより、チーム内での連携を保ちながら、日々の業務に変化と柔軟性をもたらすことができます。
フリーアドレスとの決定的な違いは「エリア指定」
グループアドレスとフリーアドレスの最も大きな違いは、社員が利用できる座席の範囲です。フリーアドレスがオフィス内のすべての席を全社員が自由に使えるのに対し、グループアドレスは所属するグループに割り当てられた特定のエリア内でのみ席を自由に選べます。
この「エリア指定」の有無が、両者の特徴を大きく分けています。
|
項目 |
グループアドレス |
フリーアドレス |
|
座席の範囲 |
部署やチームごとに指定されたエリア内 |
オフィス内の全エリア |
|
連携のしやすさ |
チームメンバーが近くにいるため、連携しやすい |
メンバーが離散しやすく、連携に工夫が必要 |
|
マネジメント |
管理職が部下を把握しやすく、管理が容易 |
部下の居場所が分かりにくく、管理が難しい場合がある |
|
導入のハードル |
固定席の運用に近く、比較的低い |
働き方が大きく変わるため、比較的高め |
フリーアドレスが持つ「自由度の高さ」というメリットを享受しつつ、そのデメリットである「チームの連携の取りにくさ」を解消した、いわば両者の"いいとこ取り"のスタイルがグループアドレスであると言えます。
グループアドレスが持つ5つの導入メリット
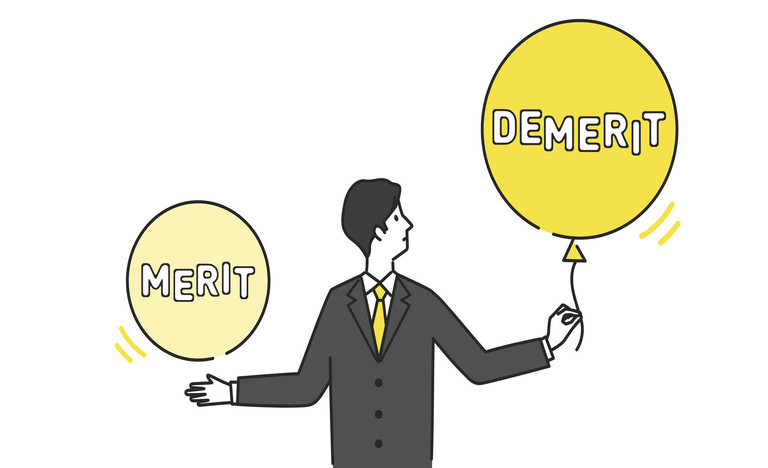
グループアドレスを導入することは、企業に多くの利点をもたらします。ここでは、特に注目すべき5つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット1:チームの一体感を維持しやすい
グループアドレスは、チームメンバーが同じエリア内で働くため、自然と顔を合わせる機会が多くなります。これにより、業務上の相談や情報共有がスムーズに行えるだけでなく、雑談などの偶発的なコミュニケーションも生まれやすくなります。
物理的な距離の近さが心理的なつながりを生み、チームとしての一体感を損なうことなく業務を進めることが可能です。
メリット2:管理職のマネジメントが容易になる
フリーアドレス環境では、部下がオフィスのどこにいるのか把握しづらいという課題がありました。しかし、グループアドレスでは、部下は必ず指定エリア内にいるため、管理職はメンバーの状況を容易に把握できます。
業務の進捗確認や勤怠管理、ちょっとした声かけなどがしやすくなり、きめ細やかなマネジメントが実現します。
メリット3:フリーアドレスより導入のハードルが低い
全社一斉にフリーアドレスを導入するのは、働き方が大きく変わるため、社員の戸惑いや反発を生む可能性があります。
その点、グループアドレスは従来の固定席運用に近いスタイルであり、変化が比較的小さいため、社員に受け入れられやすい傾向があります。
まずは特定の部署から試験的に導入してみるなど、段階的な移行が可能な点も、導入のハードルを下げています。
メリット4:部署の特性に合わせた柔軟な運用が可能
社内には、営業部のように外出が多い部署もあれば、経理部のようにオフィス内で集中して作業する部署もあります。グループアドレスは、部署ごとに運用ルールを柔軟に変えられるのが強みです。
例えば、営業部では座席数を少なめにしてスペースを有効活用し、開発部ではプロジェクトの状況に応じてレイアウトを動的に変更するといった、各部署の業務内容に最適化された運用ができます。
メリット5:オフィスコストの削減につながる
在宅勤務や外出が多い部署では、社員全員分の固定席を用意すると、常に空席ができてしまいスペースの無駄が生じます。グループアドレスを導入し、実際の出社率に合わせて座席数(在籍人数の7〜8割が目安)を最適化することで、余分なスペースを削減できます。
これにより、オフィスの賃料や光熱費、備品購入費などのコスト削減が期待できます。
押さえておくべきグループアドレスのデメリット
多くのメリットがある一方で、グループアドレスには注意すべき点も存在します。導入後に後悔しないよう、考えられるデメリットとその対策を事前に理解しておきましょう。
デメリット1:席が固定化してしまう可能性がある
グループアドレスを導入しても、結局いつも同じメンバーが同じような席に座ってしまい、実質的に固定席と変わらなくなってしまうケースがあります。仲の良い同僚の近くや、集中しやすい窓際など、特定の席が人気になりがちです。
これでは、コミュニケーション活性化という本来の目的が達成されません。この問題を防ぐためには、意識的な席替えの推奨や、座席予約システムでランダムに席を割り振るなどの工夫が必要です。
デメリット2:部署間のコミュニケーションが減少する懸念
チーム内の連携が強化される一方で、活動エリアが部署ごとに区切られるため、他の部署の社員との交流機会が減ってしまう可能性があります。組織全体の連携や、部署を横断したイノベーション創出を重視する場合には、この点がデメリットになり得ます。
対策として、部署のエリアを定期的に入れ替える「ローテーション」を実施したり、誰でも自由に使える共有スペースやリフレッシュエリアを設けたりして、意図的に部署間の交流を促す設計が重要になります。
グループアドレス導入を成功させる4つのステップ

グループアドレスの導入は、単にオフィスレイアウトを変更するだけではありません。社員の働き方そのものを変えるプロジェクトです。
成功に導くためには、計画的にステップを踏んで進めることが不可欠です。
ステップ1:導入目的を明確にし社内で共有する
まず最も重要なのが、「なぜグループアドレスを導入するのか」という目的を明確にすることです。「コストを削減したい」「部署内の連携を強化したい」など、具体的な目的を設定します。
そして、その目的を経営層から現場の社員まで、全員で共有することが重要です。目的が共有されていないと、社員は「面倒なルールが増えた」と感じてしまい、協力が得られにくくなります。説明会やアンケートを実施し、社員の理解と共感を得ながら進めましょう。
ステップ2:対象部署の選定と座席数を決定する
次に、グループアドレスを導入する部署を決定します。営業部のように在席率が低い部署は効果が出やすい一方、経理部のように紙の書類を多く扱う部署は不向きな場合もあります。
部署の業務特性を考慮し、導入対象を慎重に選びましょう。対象部署が決まったら、時間帯や曜日ごとの在席率を調査し、最適な座席数を算出します。無駄なコストをかけないためにも、現状の正確な把握が欠かせません。
ステップ3:オフィスレイアウトと必要な設備を検討する
決定した座席数に基づき、具体的なオフィスレイアウトを設計します。レイアウト変更がしやすいキャスター付きのデスクや、複数人で使える大型デスクなどが人気です。
また、個人の荷物を収納するためのロッカーやキャビネットは必須設備です。さらに、Web会議用の個室ブースや、短時間の打ち合わせに使えるミーティングスペースなど、業務内容に合わせて多様な環境を整えることで、生産性の向上が期待できます。
ステップ4:運用ルールを策定し効果を検証する
円滑な運用のためには、明確なルール作りが不可欠です。例えば、「退社時には机の上を片付ける(クリーンデスク)」「私物を置いたまま長時間席を離れない」といった基本的なルールを定めます。
ルールはマニュアル化して周知徹底しましょう。運用開始後は、定期的に社員へヒアリングやアンケートを行い、効果を検証します。「予約が取りにくい」「特定の席が占有されている」といった問題点があれば、その都度ルールを見直し、改善していく姿勢が成功の鍵となります。
導入前に確認したい!成功のための3つのポイント
導入ステップと合わせて、グループアドレスの運用を成功に導くための重要なポイントを3つ紹介します。
ポイント1:席の固定化を防ぐ仕組みを取り入れる
前述のデメリットでも触れた通り、座席の固定化はグループアドレスの効果を半減させてしまいます。これを防ぐためには、個人の意識に頼るだけでなく、仕組みで解決することが有効です。
例えば、座席予約システムを導入し、抽選で席を決めたり、一度座った席は翌日予約できないようにしたりするルールが考えられます。こうした少しの強制力が、新たなコミュニケーションを生むきっかけになります。
ポイント2:ペーパーレス化を同時に推進する
席が固定されないグループアドレスでは、多くの書類を持ち運ぶのは非効率であり、紛失のリスクも高まります。導入を成功させるためには、書類の電子化、すなわちペーパーレス化を同時に進めることが極めて重要です。
クラウドストレージを活用してどこからでも情報にアクセスできるようにすれば、席を移動する際の負担が大幅に軽減され、グループアドレスのメリットを最大限に引き出すことができます。
ポイント3:自社に合った座席管理システムを選ぶ
特に規模の大きなオフィスでは、誰がどこにいるのかを把握したり、座席の利用状況を管理したりするために、座席管理システムの導入が推奨されます。スマートフォンやPCから簡単に座席を予約できるシステムがあれば、出社時の席探しの手間が省けます。
また、システムの利用データを分析すれば、実際の座席稼働率が分かり、将来のオフィス戦略を立てる上での貴重な情報となります。
フリーアドレスと合わせて導入したいのが位置情報共有ツールです。誰がどこにいるのかを簡単に把握できるので、探したい人をすばやく見つけてコミュニケーションを取ることができます。 PHONE APPLI PLACEは、無線Wi-FiやBeaconなどの技術を用いて、社員の位置情報を見える化するサービスです。 【PHONE APPLI PLACEの機能】 グループアドレスは、チームの連携を維持しながら柔軟な働き方を実現できる、優れたオフィス形態です。フリーアドレスが持つ課題を解決し、コスト削減やマネジメントの効率化といった多くのメリットをもたらします。 本記事で紹介した導入ステップや成功のポイントを参考に、自社に最適なオフィス改革を検討してみてはいかがでしょうか。 フリーアドレス化に伴う課題と解決方法(居場所、人探し、コミュニケーション活性化)をご紹介します。【製品紹介】誰がどこに居るか分かる「PHONE APPLI PLACE」
まとめ
【無料資料ダウンロード】フリーアドレスでよくあるお悩み解決ガイド