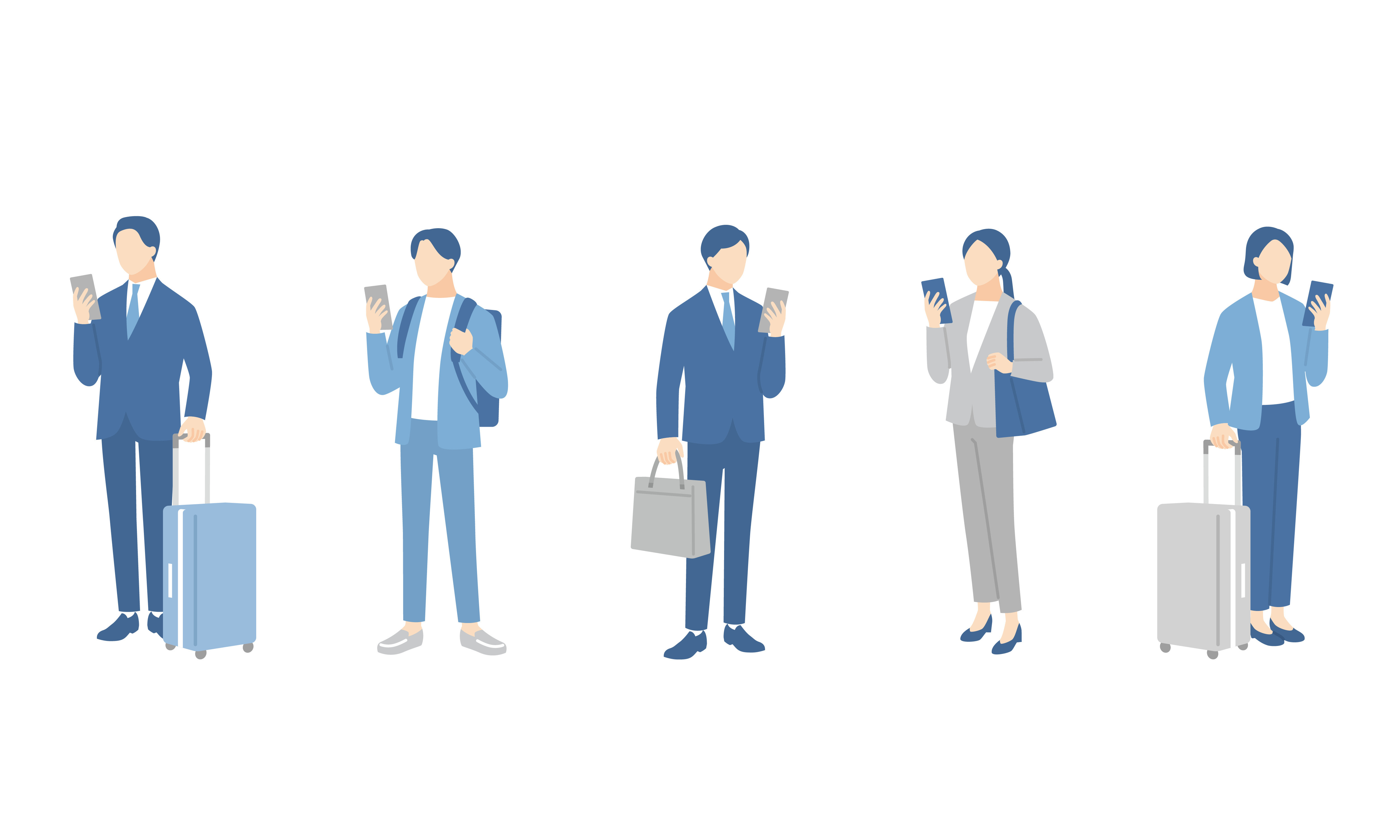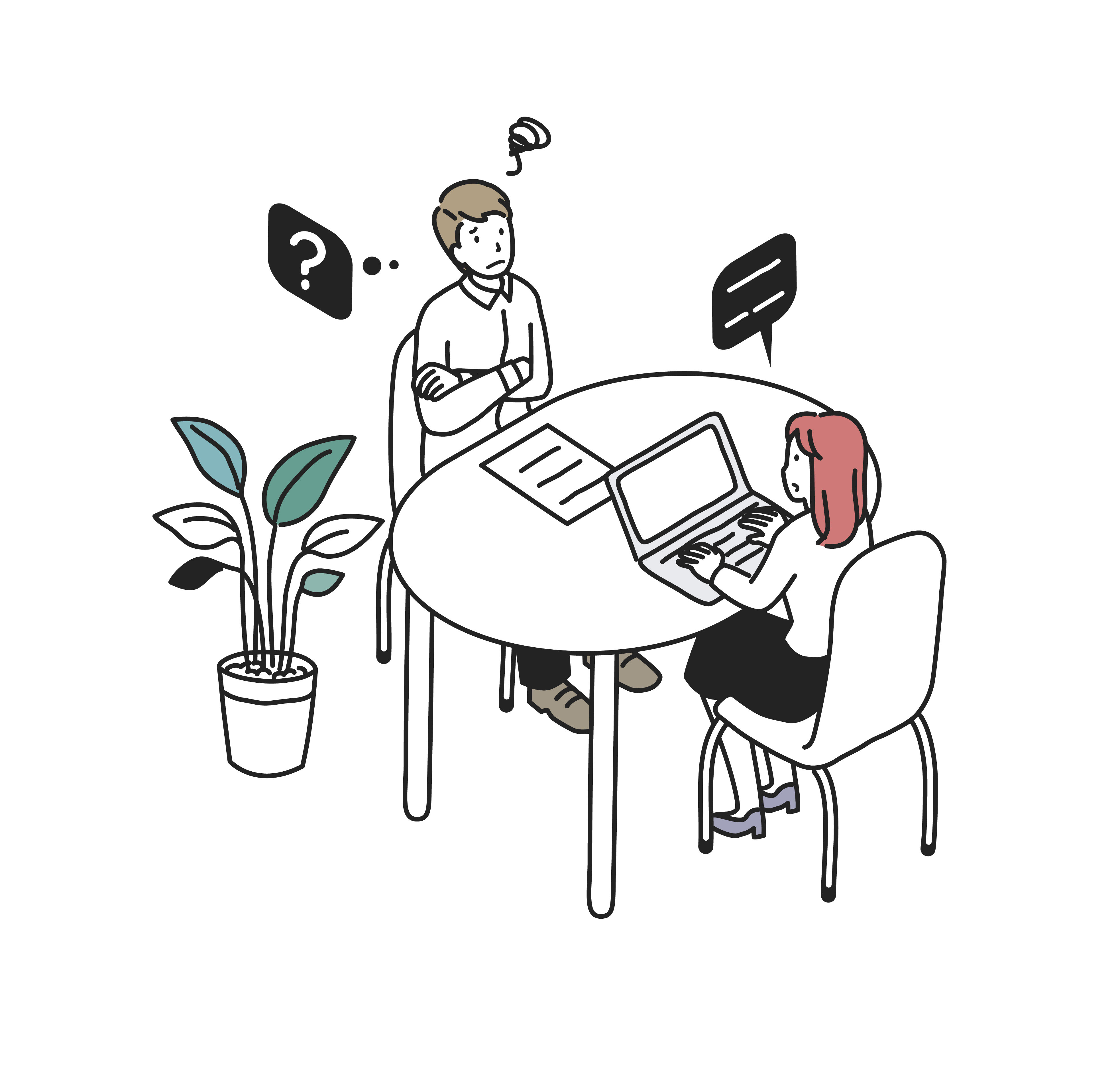サンクスカードが気持ち悪いと感じる5つの理由とは?いらない制度にしないための改善策を解説

「ありがとう」を伝え合うサンクスカード。本来は、職場のコミュニケーションを円滑にし、働く人々のモチベーションを高めるための素敵な制度のはずです。
しかし、一部では「気持ち悪い」「義務的で苦痛」といったネガティブな声が上がっているのも事実です。もし、あなたがサンクスカードに対して違和感を抱いているのなら、その感情は決して間違いではありません。
本記事では、なぜサンクスカードが「気持ち悪い」と感じられてしまうのか、その理由を深掘りし、制度が形骸化してしまう失敗例を共有します。
その上で、すべての従業員が前向きに取り組めるような、効果的な運用方法と改善のヒントを具体的に解説していきます。
サンクスカードとは?本来の目的を再確認
サンクスカードの制度に対してネガティブな感情が生まれる背景を探る前に、まずはこの制度が本来どのような目的で導入されるのかを再確認しておきましょう。
サンクスカードは、単なるメッセージカードではなく、組織の活性化を目指すための重要なツールとして位置づけられています。
感謝を伝え合うことで組織を活性化させる仕組み
サンクスカードは、日常業務の中で生まれた「ありがとう」の気持ちを、専用のカードやツールを使って従業員同士で伝え合うための仕組みです。
普段、業務に追われていると、なかなか口に出して感謝を伝えるタイミングを逃してしまうことがあります。そうした小さな感謝を可視化し、気軽に伝えられるようにすることで、組織全体のコミュニケーションの量を増やし、風通しの良い職場環境を育むことを目的としています。
コミュニケーション円滑化やモチベーション向上が狙い
サンクスカード制度の導入によって企業が期待するのは、主に「コミュニケーションの円滑化」と「従業員のモチベーション向上」です。
感謝の言葉を受け取った従業員は、自分の仕事が認められていると感じ、自己肯定感が高まります。これが仕事への意欲、すなわちモチベーションの向上につながるのです。また、普段あまり接点のない部署のメンバーともサンクスカードを通じて交流が生まれれば、部門間の連携がスムーズになり、組織全体の生産性向上にも寄与すると考えられています。
| 期待される効果 | 具体的な内容 |
|---|---|
| コミュニケーション活性化 | 部署や役職を超えた交流が生まれ、人間関係が良好になる |
| モチベーション向上 | 自分の貢献が認められることで、仕事への意欲が高まる |
| 組織風土の改善 | ポジティブな言葉が飛び交う、明るく協力的な職場環境が育まれる |
| 離職率の低下 | 会社への帰属意識や従業員満足度が高まり、人材の定着につながる |
サンクスカードを「気持ち悪い」と感じてしまう5つの理由

本来ポジティブな目的を持つサンクスカードが、なぜ「気持ち悪い」というネガティブな感情を引き起こしてしまうのでしょうか。
その背景には、制度の運用方法や、従業員が置かれている状況に起因するいくつかの共通した理由が存在します。
理由1:感謝の強要やノルマ化で義務に感じる
最も大きな原因は、「感謝の強要」です。
会社によっては「月に〇枚書くこと」といったノルマが設定されるケースがあります。こうなると、感謝の気持ちは自発的なものではなくなり、単なる「義務」や「作業」に変わってしまいます。本来感謝していない相手に対しても無理にカードを書かなければならない状況は、強い心理的負担となり、「気持ち悪い」という感情を生み出す大きな要因となります。
理由2:内容が思いつかず業務負担になっている
日々の業務で忙しい中、サンクスカードを書く時間を確保すること自体が負担になることがあります。
特に、感謝すべき具体的なエピソードがすぐに見つからない場合、何を書くべきか頭を悩ませることになります。この「内容を考える」という行為が、本来の業務を圧迫するほどのストレスとなり、制度そのものへの嫌悪感につながってしまうのです。
理由3:評価を意識したやり取りが偽善的に見える
サンクスカードのやり取りが人事評価の一部に組み込まれている、あるいは上司が内容をチェックしているような環境では、本心からの感謝ではなく「評価のための行動」と捉えられがちです。
上司に取り入るためにカードを送ったり、当たり障りのない定型文を送り合ったりする光景は、偽善的に映り、制度への不信感を募らせます。「ありがとう」という美しい言葉が、評価を気にしたパフォーマンスの道具として使われることに、多くの人が気持ち悪さを感じるのです。
理由4:人前で感謝されることへの心理的抵抗
感謝を伝えることだけでなく、受け取ることに関しても、すべての人がポジティブに感じるわけではありません。
特に、内向的な性格の人や、人前で注目されるのが苦手な人にとって、自分の行動がカードによって全社に公開される状況は、気まずさや居心地の悪さを感じる原因となり得ます。この心理的な負担が、サンクスカードへのネガティブな印象を形成することがあります。
理由5:特定の従業員間でのやり取りに偏りが生まれる
制度を運用していく中で、自然とコミュニケーションが活発な従業員や、目立つ成果を上げた従業員にカードが集中しがちです。
その一方で、縁の下の力持ちとして黙々と業務をこなしている従業員には、なかなかスポットライトが当たりません。このようなやり取りの偏りは、社内に見えない格差を生み出し、カードをもらえない従業員の疎外感や不公平感を助長する結果につながります。
「いらない制度」にしない!サンクスカード導入の失敗例
サンクスカード制度は、良かれと思って導入しても、運用の仕方を間違えると従業員のモチベーションを下げ、逆効果になってしまうことがあります。
ここでは、制度が形骸化し、「いらない」と思われてしまう典型的な失敗例を3つ紹介します。
失敗例1:目的が周知されず、ただの作業になってしまった
経営層や人事部が「コミュニケーション活性化」という目的を掲げて制度を導入しても、その重要性や背景が従業員一人ひとりにまで伝わっていなければ、意味がありません。
目的が理解されないまま「とにかくカードを書きなさい」という指示だけが現場に下りてくると、従業員は「なぜこんなことをしなければならないのか」と疑問を感じます。結果として、サンクスカードを書くことが目的化した「やらされ仕事」となり、制度は早々に形骸化してしまいます。
失敗例2:紙での運用にこだわり、手間がかかりすぎた
感謝の気持ちを伝える上で、手書きの温かみは確かに魅力的です。
しかし、紙媒体での運用は、カードの配布、記入、回収、集計といった多くの手間を伴います。特に、拠点や部署が複数に分かれている企業では、カードのやり取り自体が大きな負担となります。また、外回りの営業職やリモートワークの従業員は参加しにくく、不公平感も生まれやすいです。この運用の手間が、制度を継続する上での大きな障壁となってしまうのです。
失敗例3:経営層や管理職が参加せず形骸化した
従業員にサンクスカードの利用を促す一方で、肝心の経営層や管理職が全く参加しない、というのもよくある失敗例です。
上司が部下の働きぶりに感謝を示さなければ、部下も同僚や他者への感謝の気持ちを持ちにくくなります。役職者が積極的に活用する姿勢を見せない制度は、従業員にとって「会社は本気ではない」というメッセージとして受け取られ、誰も積極的に参加しない形だけのものになってしまうでしょう。
| 失敗パターン | 発生する問題 | 従業員の心理 |
|---|---|---|
| 目的の不徹底 | やらされ感の蔓延、形骸化 | 「何のためにやるのか分からない」 |
| 運用の手間 | 業務負担の増大、参加率の低下 | 「面倒くさい」「忙しくて書けない」 |
| 管理職の不参加 | 制度への不信感、利用率の低迷 | 「結局、現場に丸投げか」 |
気持ち悪さを解消する!サンクスカードの運用ポイント
サンクスカード制度を「気持ち悪い」ものから、本当に意味のあるものへと変えるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
従業員の自主性を尊重し、誰もが気持ちよく参加できる環境を整えることが成功への鍵です。
導入の目的と意義を丁寧に説明する
制度を始める前、あるいは見直す際には、「なぜサンクスカードを導入するのか」「この制度を通じてどのような組織を目指したいのか」という目的やビジョンを、経営層や管理職が自らの言葉で丁寧に説明することが不可欠です。
会社の目指す方向性への共感が得られれば、従業員はサンクスカードを「やらされるもの」ではなく、「より良い職場を作るための自分たちの取り組み」として前向きに捉えることができます。
管理職が率先してポジティブな手本を示す
制度を社内に浸透させるためには、特に管理職の行動が重要です。
上司が部下の小さな頑張りや貢献を見つけ、具体的に褒めるサンクスカードを送ることで、部下は「自分のことを見てくれている」と感じ、モチベーションが高まります。また、どのような内容を書けば良いかの手本にもなり、他の従業員がカードを書きやすくなるという効果も期待できます。
具体的な感謝の内容を書く文化を醸成する
「いつもありがとう」といった抽象的な言葉だけでは、感謝の気持ちは十分に伝わりません。
「〇〇の資料、グラフが見やすくてとても助かりました」「急な依頼にも関わらず、迅速に対応してくれてありがとう」のように、「何に対して、なぜ感謝しているのか」を具体的に記述することが大切です。このような具体的なメッセージが増えることで、やり取りの質が高まり、偽善的な印象を払拭できます。
手軽に送れるデジタルツールの活用を検討する
紙での運用に課題を感じる場合は、スマートフォンやPCから手軽にメッセージを送れるデジタルツールの導入が有効です。
アプリなどを使えば、場所や時間を選ばずに感謝を伝えられ、集計や可視化も容易になります。これにより、従業員の負担を軽減し、参加のハードルを大きく下げることができます。多くのサービスが存在するため、自社の文化や規模に合ったツールを選ぶことが重要です。
インセンティブや表彰制度と連携させる
サンクスカードのやり取りを活性化させるための工夫として、インセンティブの導入も効果的です。
例えば、受け取ったカードの枚数に応じてポイントを付与し、景品と交換できるようにしたり、月に一度「最も多くの感謝を伝えた人・受け取った人」を表彰したりする仕組みです。ゲーム感覚で楽しめる要素を加えることで、ポジティブな動機付けとなり、制度の定着を促進します。
サンクスカードの代替案となるコミュニケーション施策

サンクスカードが自社の文化に合わない、あるいはうまく機能しないと感じる場合は、他の方法で感謝や称賛の文化を育むことも可能です。
ここでは、サンクスカードの代替となりうるコミュニケーション施策を3つ紹介します。
ピアボーナス制度を導入する
ピアボーナスとは、従業員同士が互いの成果や貢献を称賛し、少額の報酬(ボーナス)を送り合う仕組みのことです。
「感謝の気持ち」に金銭的な価値を付与することで、よりリアルな評価として認識されやすくなります。感謝や称賛が個人の報酬に直接結びつくため、従業員のモチベーション向上に直結しやすいというメリットがあります。
1on1ミーティングの質を高める
上司と部下が定期的に行う1on1ミーティングも、感謝を伝える絶好の機会です。
形式的な進捗確認に終始するのではなく、部下の日頃の頑張りや成長を上司が具体的に認め、感謝の言葉を直接伝える時間を設けます。個別のクローズドな場であるため、人前で褒められるのが苦手な従業員に対しても、安心してポジティブなフィードバックを伝えることができます。
社内報やチャットで活躍を紹介する
社内報や社内SNS、ビジネスチャットツールなどを活用し、従業員の隠れた功績や素晴らしい取り組みを全社的に共有する方法も有効です。
特定の個人へのサンクスカードという形ではなく、チームの成功事例や顧客からの感謝の声などを紹介することで、多くの従業員の貢献を可視化することができます。これにより、特定の個人に称賛が偏ることを防ぎ、組織全体の士気を高める効果が期待できます。
| 代替施策 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| ピアボーナス | 従業員同士で少額の報酬を送り合う | モチベーションに直結しやすい、評価の納得感が高い |
| 1on1ミーティング | 上司と部下の対話の中で直接感謝を伝える | 個別対応が可能、心理的安全性を確保しやすい |
| 社内報・チャット | 全社へ向けて従業員の活躍を発信する | 多くの人の貢献を可視化できる、不公平感が生まれにくい |
PHONE APPLIが実践している「従業員のエンゲージメントを高める取り組み」について
ここでは、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。
従業員間で感謝や称賛を"贈りあう"「PHONE APPLI THANKS」の活用
「PHONE APPLI THANKS」は、従業員間で感謝や称賛を"贈りあい"、組織のパフォーマンスを向上させるウェルビーイング経営推進サービスです。日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして"贈りあう"ことで、従業員それぞれの様子が見えるようになり、認め合う組織風土を育むことができます。
【PHONE APPLI THANKSの特長】
- 日々で感じた感謝や称賛をメッセージにして送り合える
- やりとりがオープンに表示されるため社員の活躍を把握しやすい
- メッセージカードに「いいね」を押すことができる
サンクスカードをお手軽に導入しませんか?
「PHONE APPLI THANKS」は感謝や称賛を"おくりあい"組織のパフォーマンスを向上させるサービスです。日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして"おくりあう"ことで、認め合う組織風土を育むことができます。こうした風土が社員間の心理的安全性や、働くことに対する幸福度を高め、組織の健康経営にも寄与します。
組織の幸福度を測定する「Well-being Company Survey」の活用
- Well-being Company Survey とは、幸福経営学研究の第一人者ホワイト企業大賞委員長である天外伺朗氏と慶応義塾大学 前野隆司教授協力のもと、 PHONE APPLI が開発したパルスサーベイです。
Well-being Company Surveyの詳細はこちら
「1on1ツール」を活用し、週25分の対話でメンバーの状態を把握
- 1on1ツールで現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、話したいトピックを選択します。それにより、マネージャーがメンバーの状態を把握しやすくなり、1on1の質が高まりました。また、全社横断での1on1も積極的に実施しています。組織横断コミュニケーションを意識的に増やすことで、精神的・社会的健康の向上を目指しています。
ウォーキングイベント「PA Walking Cup」で運動習慣の定着化
運動習慣の定着を目的としたウォーキングイベント毎月開催しています。従業員が楽しく参加できるよう、季節ごとのテーマやゲーミフィケーションを取り入れながら工夫しています。
年齢制限なしの保健指導で若年層の健康リスクにも対応
40歳以上の特定保健指導対象者だけでなく、39歳以下の生活習慣病予備群にも年齢制限を設けずに保健指導を実施しています。将来の疾病リスクを低減し、特定保健指導対象者の若年層からの流入抑制を目指しています。
まとめ
サンクスカードが「気持ち悪い」と感じられるのは、制度そのものではなく、感謝を強要するような運用方法に問題がある場合がほとんどです。
ノルマ化や形骸化を避け、従業員の自発性を尊重することで、サンクスカードは本来の目的である、組織の活性化やモチベーション向上のための強力なツールとなり得ます。本記事で紹介した運用ポイントや代替案を参考に、自社の文化に合った感謝を伝え合う仕組みを築いてください。大切なのは、従業員一人ひとりが心からの「ありがとう」を気兼ねなく伝えられる、ポジティブな職場環境を育んでいくことです。
サンクスカードをお手軽に導入しませんか?
「PHONE APPLI THANKS」は感謝や称賛を"おくりあい"組織のパフォーマンスを向上させるサービスです。日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして"おくりあう"ことで、認め合う組織風土を育むことができます。こうした風土が社員間の心理的安全性や、働くことに対する幸福度を高め、組織の健康経営にも寄与します。